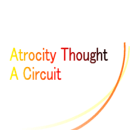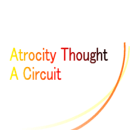甘い甘い罠
俺は、鼻歌まじりに明日の朝食と
愛するナミさんと、ロビンちゃん達の為に甘ーいスウィーツを作り始める所だった。
今日停泊した街で、初めて見た調味料を試してみたくて早速準備を進めていた。
俺は、見たこと、使ったことのない調味料を見つけると、買わずにはいられない性分でついつい買ってしまう。
店の店主に聞いたら、この調味料を使うととても美味しいスウィーツになるんだとか。
どんな味なんだろう。
香り付けに使うものか?
この俺としたことが…店主に使い方しか聞いてこなかった。
とりあえず、香りは?
調味料に鼻を近付けてみた。
が、
香りはない。
では、味?
小指に一滴垂らし、ペロリと一舐めした。
コクと深みがあって何ともいえない甘さだ。
『これなら、お菓子に入れると美味しくなりそう』俺は一人で、微笑みながらお菓子作りに手を付けた。
始めて10分程経った頃、体に異変が起こり始めた。
体温が異常に上がっていっているような感覚から始まり、
徐々に呼吸が苦しくなってきた。
酸素を吸っても、肺に取り込まれないような息苦しさ。
一番おかしいのは体が敏感になってきた事だ。
少し動いただけでズボンの摩擦で俺の息子が勃ってしまった。
それが今にもイきそうなくらい、感じてしまってかなりマズい状況に。
早くトイレに行きたい。
俺は前かがみになりながら、壁を伝って歩いていくが
少し動くだけで堪らなく感じてしまう。
素肌に着たシャツが胸元や首筋を擦ると背筋に電気が走ったようにゾクゾクと快感を与えてくる。
「…これ…やべぇな…」
息を切らし、誰にも会いませんようにと祈りながら一歩一歩前に進む。
いつもなら、トイレなんてすぐなのに
今日はやけに遠く感じる。
ようやくトイレに着いて、入ろうとすると鍵がかかっている。
誰か入っているようだ。
ドアをノックすると、中から聞き慣れたゾロの声が。
「入ってる、もう少し待ってろ。」
「もう…待てねぇ…早く…しろクソヤロウ…」
いつも通りに言ったつもりだったが、やはり感じが違ったか、すぐ扉は開けられた。
俺は、立っているのも、耐えられず壁に寄りかかっていた。
「なんて顔してんだよ…誘ってんのか?」
ゾロは俺の表情を見ると、ため息をついた。
トイレの中に掛けられた鏡に視線を移した。
鏡に映った俺の頬はピンク色に染められ、薄く開かれた口元から、息苦しそうに呼吸をしていたし
瞳は、物言いたそうに潤んで
そう言われても仕方ない表情をしていた。
「あほか…早く…どけ…」
「あぁ…」
ゾロとすれ違いざまに、肩が少し触れた。
「…っ!?…あ…っ!!!」
俺は、たったそれだけで傍にいたゾロに思わずしがみついてイってしまった。
下着が、精液で濡れて肌にまとわり付いて気持ち悪いのに
それもまた快感に繋がってしまう。
ゾロがその表情を見た瞬間、俺の腕を掴みどこかへ連れていこうと歩き出した。
「…っめろ…離せ…なに考えてんだよ…てめぇ…」
食料庫に連れ込まれた。
腕を掴まれただけで快感が体中に広がり、抵抗も出来なかった。
ゾロは無言で、俺を強引に酒樽の上に座らせて唇を重ねてきた。
こいつに主導権を握られるなんて、気に入らん。
が、今回は無理だ…。
身体も頭も快感で全然云うことをきかない。
ゾロの舌が口内を弄り、体中を服の上から触られると簡単にイッてしまった。
「我慢きかねぇ。てめぇが俺にエロい顔を見せるのが悪い。」
「ざけんな!!知るかっ…」
唇を再び塞がれ、器用に俺の服のボタンを外していく。
「んっ…やめ…っぁ…」
ズボンも下着と一緒に脱がされた。
脱がされた下着はベトベトに濡れて俺の肌から離れる時、透明な糸を引いた。
「すげ…、こんなに下着が濡れるほど短時間でイッちまったんだ。
いつから、こんなにエロい体になったんだよ」
まじまじと俺の下着を見つめ、その視線はそそり立つペニスに向けられた。
「見んなっ…!!今日は体がおかしいんだよ…いつもはこんなんじゃねぇ」
慌てて、手で隠した。
その手は強引にどかされ、ゾロは俺のペニスを口にくわえた。
「ひっ!!!…っ…ああぁん…っんぅ…やめ…」
思わぬ事に変な声が出てしまった。
「サンジの味がする…」
俺は恥ずかしくて、顔を火照らした。
「てめっ…やっ…やめろっ…離せ…くち…やめっ…でる…でるから…」
俺の言葉を聞くと、より一層激しく吸い上げ、舌を絡ませてきた。
口の中が気持ちよくて腰がとろける、我慢できない。
「ゾロっ…っ!!!」
ゾロの頭を夢中で押さえつけて、口の中で射精した。
ゴクリと喉を鳴らして飲み込んだ音が小さく聴こえた。
少し放心状態になっていた俺にゾロの声は遠くて良く聞き取れなかった。
「すげぇな…こっちも、舐めてほぐしてやる。」
「…」
樽に手をつき、腰をゾロの顔の前に突き出す姿勢に促された。
「…なに…ひっ!!?」
ぼーっとした頭に快感という衝撃が加えられ、
考えるより先に体がビクビクと反応する。
ゾロの熱い舌が、堅く閉じた蕾を開こうと
舌先で蕾をくすぐる。
「それ…嫌だ…」
「もう、ダメだ。
本当に我慢きかねぇ。
挿れるぞ」
「…は?ムリに決まってる…準備…」
ゾロはアナルに自分のペニスをあてがい、準備もなく俺の胎内に侵入した。
「あ゛―っ…!!!!あっ、あぁ…っ…んぅ…っ…やぁイッ…」
「馴らさなくても、すっげぇ柔らかくてきゅうきゅう締め付けてくるぞ。」
「クソ…まりも…っぁあ!!!」
「こんな時まで悪態つきやがって!!いい声で鳴けよ」
より一層、胎内を掻き回され俺は甘い声を上げ続けた。
何度も何度も、精液を吐き出し
ゾロにすがりついていた。
「ぁ…あ…ぁぁっ!!…ゾ…ロぉ…気持ちぃ…っ…気持ち良すぎておかし…なるっ」
ゾロが奥をえぐると、快感で体がビクッと反応して恥ずかしい。
しかし、もっとして欲しいという欲求が収まらない。
奥を突かれると、体がもっとゾロが欲しいと要求する。
突かれる度に、何も考えられなくなって体もいうことをきかない。
俺が俺でなくなる…そんな感覚が脳内を満たす。
「あっ…ぁっ…んっ…イイ…もっと擦っ…もっと…」
体中が敏感になっていく。
もうどこを触られてもイってしまう。
時間も頭も体も訳が分からなくなった頃、俺は快楽の中で意識を失った。
いつもと様子がおかしい。
床に横たわったサンジの体に毛布を掛け、そっと食料庫を後にした。
廊下を少し進むと、チョッパーが薬を調合していると思われる音が部屋から聞こえてくる。
その部屋の扉を静かに開けた。
「チョッパー、まだ起きてるか?」
「おう、いま薬を調合してたところだ。どうかしたのか?」
「あぁ、サンジの様子がおかしいんだ。
今日は立っているのも辛そうな程、体が敏感になっているらしくて…
なんていうか…その…すげぇ、色っぽいっていうか…。」
「ん─?ちょっと、いっている意味がわからないけど
…思い当たる節がある。
サンジの様子診れるか?」
「あぁ、食料庫にいる」
チョッパーを連れて、食料庫に戻るとサンジが目を覚ましていた。
毛布に包まったまま熱っぽい表情を浮かべている。
「サンジ…大丈夫か?今、心配したゾロから様子を診てほしいと頼まれたんだ。
ちょっと、触って様子を診させてくれ。」
「あぁ…」
目、口の中、脈といった普通の事に対しても反応を抑えられないくらい敏感になっている。
『俺の体はどうしちゃったんだ。』
チョッパーに触られただけで、股間が熱くなって恥ずかしい。
「ん…これ…おれの思ってたとおりだ。
おれがみた文献と同じ症状が出てる。」
チョッパーが俺の右腕にある青色のあざをみつけた。
「なんだ…これ」
「チョッパー、これ花の様にみえるな」
「あぁ、これは…
『セフィブルー』という名前の植物の蜜を摂取するとあらわれるあざだ。
その名前の通り、青色の小振りな花が咲く植物で、その蜜はそのまま使うと強烈な媚薬。
熱処理をして使うと最高の調味料そう云われてる。
だけど、最近かなり巷で問題になっていて、犯罪に使われるケースが多くなってきてるみたいなんだ。
サンジも…
これを舐めたに違いないと思う。
直す方法が…あるのは…確かだ…。
だけど、その調合する材料が問題で…。
あんまり使わない材料だから…ストックがないんだ。
それに…手に入りにくい材料だ。
港に寄って貰っても、あるかわからない…。
サンジの状態も薬を飲まなきゃ、ずっとこのまま…
ただ…」
言葉を続けないまま、しょんぼりと肩を落とすチョッパー。
「ただ…?
何か、他に方法があるのか?」
サンジを横目で見ながら、チョッパーに尋ねる。
「あ…あるといえば…ある。
けど、この方法は嫌がると思う…」
「今は、嫌がってる場合じゃねぇよ…
なんでも治るなら…方法言ってくれ」
熱っぽい表情をチョッパーに向けた。
チョッパーは、困った表情を浮かべて口を開いた。
「サンジは…精液…飲めるのか…?」
「な…なに…?」
動揺を隠し切れない。
そんなもの好んで飲んだ事はない。
「…精液なんだ、薬の代わりになるの…
成分がほぼ一緒だから、飲めば治る。
ただ、結構な量を飲まなきゃいけない。
薬を飲むのと違うから成分が凝縮されてない。」
「遠まわしに言うなよ…いったい、どのくらい飲めば俺は治る?」
何故か、冷静になってきた。
受け入れようという気持ちに、不思議となってきたのだ。
「最低でも、5回分だ…。
おれもそんなことした事ないから、わからない。
成分の摂取量を計算すると、最低でも5回分飲めば治る計算だ。
でも、保障はできないぞ!
おれは、とてもじゃないけど…出来ないし。勧められない…」
「わかった…なんとかしてみる。
この状態で居続けるのは身体がもたねぇ…。
二人とも…出てってくれるか」
「一人で何とかするつもりか?」
「あぁ…二人とも、悪ィな…。外に出ててくれ…。」
サンジは、だるそうに立ち上がるとゾロとチョッパーの背中を押して
ドアに向かわせた。
チョッパーが心配そうな表情で振り向くが、部屋の外に出ていった。
ゾロは部屋の外には出ず、扉を締めた。
「てめェもでてけよ…」
「でていかねェ…手伝ってやるよ」
「手伝いなんて…」
「いらねェわけねェだろ?飲めんのかよ」
サンジは、黙ってしまった。
情事の中で無理矢理ゾロのを飲まされたことがあるが…出来れば飲みたいものではない。
「とりあえず、オレのをくわえろよ」
ズボンと下着を少し下げ、ぺニスをサンジの顔の前に晒す。
「くっ…オレに命令すんな…オレがしたいようにする」
不服そうな表情を一瞬見せたが、素直に舐め始めた。
「っ…ふっ…さっさと出せ。…クソ野郎…」
素直だと思い始めた矢先にこれだ。
少し凝らしめようと、ピンク色に尖った乳首に触れると
思っていた以上の反応を見せた。
「ひっあ!…っやめ…ろ…」
忘れていたが、今は酷く敏感になっているのであった。
毛布の隙間から露になった下半身は、腹にくっついてしまいそうな程
そそり立っており、サンジは直ぐに達しないように
手で押さえ付けていた。
「もう、イきそうなのか…?」
「はっぁ…さっきから…限界がきてる…手…離したらイっちまうんだよ…」
「もう我慢しなくていい」
「え…っ…」
サンジの体を離し
ゾロがサンジのペニスを口に含み舌を這わせる。
「っ!!!?っ…ぁ…」
すぐにサンジは身体を痙攣させて、口の中に熱い液体を吐き出した。
「っ…わり…ィ…」
逃げられないようにサンジの顎を掴み唇を重ねた。
舌を絡め、唾液と混ざった精液を口移しで飲ませる。
「ぇっ…!?ぃっ…」
案の定、顔を背けようとしたサンジの頬をしっかり手の平で押さえ
鼻をつまんで飲み込ませた。
「まだ、一回目だぞ。
今から嫌がっててどうする?
自分でやるって言い出したんだろ」
鼻で嘲りながら云うと
舌打ちしながら
ゾロのペニスを口に含んだ。
何回やっても慣れないフェラ。
全く達っせる気がしない。
「ちょっと苦しいぞ…」
サンジ頭を軽く掴み、ゾロ主導で喉の奥までピストンを繰り返した。
涙を浮かべながらも、従うサンジ。
絶頂を迎えそうになると、自然に手に力が入って
サンジを頑固に扱っていた。
「んっ…ぅ…ぅ…」
苦しいのはわかっていた。しかし、快感の波が次から次へと引き寄せて
それを制御出来る余裕はない。
「…はぁ…っでる…飲めよ…」
サンジが逃げないように、しっかり頭を押さえつけて口の中に吐き出した。
「ぅ…っ…」
ゴクッと喉が鳴るのを確認して、口からペニスを抜く。
――――――
それから、時間を掛けて4回程サンジに精液を飲ませた。
チョッパーから言われていたのは最低でも5回という事だったが
効果が解らない為、合計6回飲ませた。
すぐには、効果が出ないだろうという結論に至り
サンジを風呂に入れて
翌朝様子をみることにした。
翌朝―――
目が覚めたとき、サンジは部屋に居なかった。
まだ、ルフィ達はぐっすり眠っていた為、
静かに部屋を出て、サンジが居そうなキッチンに向かった。
キッチンに近付くと、包丁が調子良い音を奏でていた。
キッチンに入り、サンジの姿を確認する。
「調子はどうだ?」
「おぉ、一応…
てめェのおかげで…
だいぶ…良くなった。
悪かったな…」
恥ずかしさからか、顔を上げずに応えが返ってきた。
みるとサンジは、耳まで真っ赤に染めていた。
「そりゃ、よかった。」
素直に礼を言う照れるサンジに笑いが込み上げてきたが
ここで笑うとケンカになるので、我慢して所定の席に着いた。
110516
春夜
|