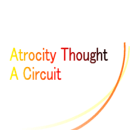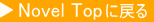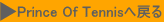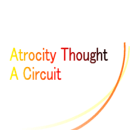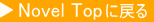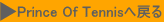HappyHappyBirthday 5
次の日の放課後
桃城が朝練に行くためにコートへ向かうと、
すでにコート内にはレギュラー陣が何人か練習を始めていた。
「おっす!海堂!」
後ろから桃城に声をかけられ、コート内に一緒に入っていく。
「・・・おう・・・」
めずらしく海堂はバンダナを付けていない。
桃城が声をかけたとき、何かを握りしめている右手をそっと見えない位置に隠した。
「今日は、バンダナしないのか?いつもしてるのに」
バンダナをしていない海堂を不思議に思い問いかける。
「・・・する・・・けど・・・」
何故か顔を赤くして、何かを隠しているような素振りを見せる。
「ん?何隠してるんだ?」
海堂が隠しているものが何か知りたくて、海堂に詰め寄る。
「なっ、何でもないっ!・・・あっ、バカっ!やめろっ・・・わぁ!?」
海堂の逆をついて反対から手を伸ばした桃城は海堂の右手を掴む。
「あっ・・・これ、俺があげたやつ・・・早速使ってくれんのか?ありがとな!嬉しいぜ!」
自分があげたのを使おうとしてくれている海堂を抱きしめたい衝動に駆られたが、
殴られそうなので止めた。
「・・・っ」
何か言い訳をしようと思った海堂だが、桃城が満面の笑みで喜んでいたため、
喉まで出かかっていた言葉を飲み込んだ。
そして、他の部員達に怪しまれない内に、バンダナを慣れた手つきで巻いた。
「あ、みんな集まってきてるから部長のとこ行こう」
コート中心部を見るとレギュラー陣が整列するところだった。
走って大石や不二が並んでいる所に桃城達も一緒に並んだ。
整列したとき海堂は自然に桃城と菊丸に挟まれるような形になってしまっていた。
「あれ、今日は珍しい。海堂と一緒なんだ?おチビちゃんは連れてこなかったの?桃」
菊丸は不意に桃城に声を掛ける。
「あっ・・・ああ・・・今日は用事があったから越前の家に寄れなかったんですよ。」
不意にいつも一緒にいる越前が居ないことに触れられて少し動揺した。
「ふーん・・・最近、海堂と桃、一緒にいること多いよね。」
菊丸は更につっこむ。
話を聞いていないようで全部聞こえている海堂は、内心ビクビクしていた。
「そ・・・そうっすかね?俺は、そんなこと無いような気はするんすけど・・・」
菊丸の鋭い突っ込みに、内心桃城も焦る。
「いーや、喧嘩の回数も減ったしね。」
菊丸は楽しそうに笑って海堂を見る。
すると、ふと海堂のジャージの襟ギリギリで隠れそうな首のラインに違和感を感じた。
「やだなー英二先輩ったら〜。そんなこと無いっすよ?この前もケンカしたし、その前も・・・」
焦りながら言い訳を並べる。
「あれ?海堂。その首どうしたの?赤くなって・・・あ・・・もしかして、もしかすると?」
桃城が喋っている途中なのに菊丸の意識はそこには無く、すでに海堂へと移っていた。
「あ・・・ヤバイ」
桃城は小声で呟いて苦笑いを浮かべた。
「え?首ッスか・・・?・・・っあ!!」
最初は何のことかぴんとこなかった海堂だが、数秒後バッとものすごい速さで首のそこを手で押さえた。
「な〜にかにゃ〜?先輩にいってみにゃ〜?」
怪しげな笑みを浮かべて近寄ってくる。
「・・・いやっ・・・これは・・・蚊に・・・」
手でそれを押さえたまま適当なことを口走りながら後ずさっていく。
「今の時期に、蚊はいないにゃ〜。見せてみなさい?」
更に近付こうとする菊丸。
「っじゃあ・・・じんましんで・・・」
すでに海堂は冷や汗をにじませている。
キッと桃城を睨んで「なんとかしろ」と訴えている。
「じゃあって言っている時点で嘘だって分かるよ!見せてよ海〜堂〜!
それ、キスマークなんだよねぇ?」
大きい声で海堂に問う。
「どうしよう・・・」
桃城は小さく呟いた。
付き合っている事を話そうか迷っているのだ。
「そっ、そんなわけないじゃないッスか!!」
海堂は必死に弁解するが顔は真っ赤に染められている。
「本当にそうかにゃ〜?真実をはにゃしてみにゃさい!!」
ニヤニヤと鋭い笑みを浮かべている。
「うっ・・・」
じりじりと菊丸から後ずさりする。
「薫・・・すまん・・・」
海堂とすれ違い様に、小さく呟く。
そして、海堂の楯になる様に桃城が前に出る。
「もっ・・・桃城・・・?」
息を呑むように前に立った桃城の後ろ姿を見つめる。
「英二先輩・・・これ以上、海堂を追いつめないでくれますか・・・」
海堂を隠すように立ちふさがる桃城に、菊丸はビックリしていた。
「ちょっ桃っ・・・・何言ってんだ・・・・」
一番ビックリしている海堂も、桃城の発した言葉に表情が和らいでいた。
「ゴメン・・・薫・・・。薫が責められてるの見てられねー・・・」
辛そうな笑顔を海堂に向ける。
「・・・・桃」
その表情を目にした海堂は何も答えられなくなった。
「なに?なんだよー桃〜?」
菊丸には二人の会話が聞き取れなかったのか、不振な顔をしている。
「薫のキスマーク。付けたの俺です。それで、気が済みました?」
菊丸に向かって、少し怒っている素振りを見せた。
「えっ、やっぱり桃なの!?わーやっぱりかぁ」
菊丸は詫びれもないような言い方で戯けた。
そして、ちょっと腰を曲げて桃城の後ろにいる海堂を見た。
「もう、薫の事茶化さないで下さい。本当に怒りますよ?」
海堂を見ようとした菊丸の前に立って、少し睨んだ。
「っ・・・わかったよ・・・そんなに怒るなよ・・・・・」
菊丸は少しだけシュンとなると海堂に向かって謝った。
「分かってくれれば、いいんです」
いつもの優しい話し方で菊丸をなだめた。
「薫・・・ゴメン・・・どうしても許せなくて・・・・こんな・・・」
今度は、桃城が海堂に対してシュンとなってしまった。
「・・・・・もう、言ったことを、とやかく言うつもりはない・・・・けど」
そこまで言った海堂は言葉を詰まらせ、俯いてしまった。
「やっぱり、マズかったかな・・・言っちゃったの・・・」
海堂の顔を覗き込む。
「だから・・・・・どっちにしろ、もう・・・遅いし」
俯いて髪の毛で隠れた耳がほのかに赤くなっているのが見えた。
「そうか・・・」
桃城も俯いて黙ってしまった。ふと、二人の世界から帰ってきた桃城は、
周りがザワザワしているのに気付いた。
周りの騒めきは、二人が付き合っていた事実を知ったことの驚きの声だった。
その声を耳にした海堂は居たたまれなくなったのか、
部活中のコートを平然としているかのようにゆっくりと歩いて出ていった。
「えっ?おい!薫・・・」
桃城も、この場の雰囲気の悪さに海堂の後を追って出て行ってしまった。
その様子を見ていた手塚は、はぁ〜とため息を付いた。
「うーん、なんとも面白いことになったね」
いつの間にか現れた不二は手塚の隣で腕を組んで楽しそうに笑っている。
「俺にとっては、頭が痛くなる原因が増えただけだ。」
全く驚きもせずに、返答をする手塚。
「あれ、そうなの?二人の応援はしてあげないの?」
不二は首を傾げて微笑んでいる。
「応援するも何も・・・・・・・俺には関係ない」
少し気になる間があったが、手塚はそっぽを向いてしまった。
「ふーん・・・・そうなの」
不二は少し機嫌が悪いような声を出して背を向けた。
「何だ?不二・・・。何で、不二が機嫌を悪くするんだ?」
なぜ、そんなに機嫌を悪くするのか分からずに混乱する。
「べつに。この話の続きは個人的にね。今そんな話したら困るのは部長だよ」
あえて「部長」と呼んで周りが集まっているのを気付かせた。
「あっ、ああ・・・」
困ったような顔を一瞬だけ見せて、いつもの手塚に戻る。
そして部員にランニングを指示した。
桃城は、海堂を追って行ったが途中で見失ってしまった。
必死で探すが、なかなか見つからない。
「・・・・はぁ。もう帰ろう」
桃城は少しため息をつくと家路へ向かった。
その時・・・正面にとぼとぼ歩く海堂を見つけて海堂の名前を呼んだ。
「薫!!はぁ・・・はぁ・・・やっと見つけた」
振り向いた海堂に駆け寄り、強く抱きしめた。
「もっ・・・・!?」
なにがなんだか分からないまま、されるままになっている。
しかし、真っ昼間の外ということに気付いた海堂はとりあえず家へ入るように言ってみた。
「あっ・・・ごめん!」
それに気付いて、パッと海堂を離す。
「・・・・入れよ」
玄関を開けて中へ通す。
「えっ?いいのか?」
頷く海堂を見て、家の中に入る。
「・・・・・・」
そのまま何も言わずに飲み物を差し出して自分の部屋のソファーに座った。
「ありがと・・・」
無言の空間が広がる。
カランという、グラスの中に入った氷が崩れ落ちる。
「・・・桃・・・・ありがと・・・・・」
先に沈黙を破ったのは海堂だった。
「ああ・・・別に・・・」
照れ隠しのために、言葉づかいがぶっきらぼうになる。
「なぁ、そっち行ってもいい?」
「・・・・・」
一瞬ビックリした表情をして顔を赤く染めて小さく頷いた。
ボスッと海堂の隣に座る。
「・・・・・」
ちらっと横目で桃城を見た。
「・・・・・・」
桃城も同じタイミングで海堂を見たため、海堂と目が合って離せなくなってしまった。
そして、そっと桃城の唇が海堂の唇に優しく重なった。
「ん・・・・・・」
唇が触れ、海堂は目を閉じた。
「・・・好きだ・・・薫・・・」
唇を離して、強く抱きしめた。
「・・・・」
海堂も桃城の背中に腕をまわし桃城の気持ちに答えた。
「大好きだよ・・・」
桃城の言葉は海堂の耳にいつまでも残っていた。
FIN
←HappyHappyBirthday 4 に戻る